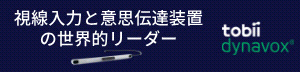2013年5月、歩行に障害を感じて病院の整形外科を訪ねた。その5年前その病院の整形外科で脊柱管狭窄症の手術を受けていたので、同様の症状が出たのではないかと思ったからである。診察と検査の結果、院内紹介で再度、神経内科で受診することになった。そして即刻、検査入院となり、8日間の入院の最終日、家内と二人で、主任看護師が同席した、主治医の説明を聞くことになった。
主治医は用紙に図を描きながら運動ニューロン病から説明を始め、嚥下障害や呼吸障害の重大な病状が発症した場合の対応を詳しくそして淡々と説明した。ALS(筋萎縮性側索硬化症)という病名はそのときはじめて聞いたが、病状が進行した様子は以前TVの報道番組で見たことがあった。しかし私は主治医の説明を心静かに聞いた。私が冷静沈着であったからではない。ALS患者になったことに現実感がなく、他人事のように思えたからである。
診断後も、「特定疾患医療受給者証」の申請、日本ALS協会への入会申し込み、「身体障害者手帳」の交付申請、市が福祉事業として行っている身体障害者向けのリハビリの申込み等の諸手続きを、まるで日常の作業を行うかのように逐次、事務的に済ました。
私が、疾患を自分自身の重大な問題として自覚したのは、診断後1年余り経ってからのことである。私は、検査入院時、すでに杖歩行であったが、1年余が過ぎたころには歩行速度は従前の半分に、歩行の持続距離は100メートル余りまでに短くなっていた。そして、路上で転倒し、救急車で搬送され傷の手当を受けるというアクシデントに見舞われたとき、愕然とするとともに身体機能の変化を否応なく直視せざるを得なかった。この事故によって決定的に私は自分自身の疾患を受け入れた。
このときを境にして、私は自分が変わったと思っている。今までは目に付かなかった国内外のALS患者の著した著作や手記をまず読み始めた。たとえば、スーザン・スペンサー=ウェンデル著、『それでも私にできること さよならを言うまでの一年の記録』(講談社 2013年)を読んで、その生命力に満ちた生活に感動を覚え、「生きる力」編集委員会編『生きる力』(岩波ブックレット 2006年)では、人口呼吸器装着の決断をさせたものは、「生きていてほしい」という家族の一言だったということに心を打たれた。また、ALS患者・家族の交流会に参加を始めたのもこの頃からである。2014年10月に日本ALS協会主催の徳島での講習会に出席し、そして全国交流会に参加した。その一ヶ月後、私の住む奈良市の患者・家族の交流会に参加した。交流会に参加して得たものは、人とのつながりであった。
「病気は神様の贈り物」が家内の口癖である。「人は病を得るたびに、何かしら得るものがある」というのがその意味だという。贈り物が絶えない家内の言だけに、その言葉に真実味がある。私はALS患者になって、これまで目にすることのなかった文章に接し、今まで知ることのなかった人の生き方に触れた。通常なら出会うことがなかったであろう人々との出会いがあった。そして自分の世界が広がった。私は大きな贈り物を受けたのである。
(2015年1月号の機関紙「JALSA」94号から転載)

2009年9月 スイス・ローザンヌIOC本部前にて